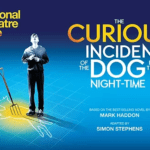<映画レポート>「脳天パラダイス」
【ネタバレ分離】昨日観た映画、「脳天パラダイス」の鑑賞レポートです。
もくじ
映画基本情報
タイトル
「脳天パラダイス」
2020年製作/95分/R15+/日本/配給:TOCANA
キャスト
昭子:南果歩/修次:いとうせいこう/ゆうた:田本清嵐/あかね:小川未祐/玄理/村上淳/古田新太/謎のホームレス:柄本明
スタッフ
監督: 山本政志 /脚本:金子鈴幸,山本政志/エグゼクティブプロデューサー:大江戸康/プロデューサー:村岡伸一郎/アソシエイトプロデューサー:根本礼史/コープロデューサー:大高健志/キャスティングプロデューサー:関谷楽子/アシスタントプロデューサー:翁長穂花/撮影:寺本慎太朗/照明:渡邊大和/録音:光地拓郎/美術:木岡菜津貴/衣装:宮本まさ江/現場衣装:津田大/装飾:岩間洋/特殊スタイリスト:百武朋/メイク:佐々木ゆう/操演:羽鳥博幸/特殊効果:羽鳥博幸/編集:小原聡子/助監督:佐和田惠/演出補:平波亘/振付演出:南流石/メインテーマ:Oto/特機:塩見泰久/技術コーディネーター:豊里泰宏/VFXディレクター:中口岳樹,島田欣征/ドローンオペレーター:池田佳史,山本雅映/庭師:高見紀雄/スチール:江森康之/メイキング:永山正史/テクニカルスーパーバイザー:溝口洋/賽本引き指導:柳川竜二/撮影協力:井戸賢生
公式サイト
脳天パラダイス
(公開後、一定期間でリンク切れの可能性あり)
映画.comリンク
作品解説
「ロビンソンの庭」「闇のカーニバル」などで知られる山本政志監督が、ある豪邸に集ったさまざま人たちの狂騒をハイテンションで描いたトランスムービー。演劇ユニット「コンプソンズ」の金子鈴幸が脚本を手がけ、南果歩、いとうせいこう、田本清嵐、小川未祐、柄本明らが顔をそろえる。
あらすじ
東京郊外の大豪邸に暮らす笹谷一家。父・修次の破産により、一家はこの家を手放すこととなった。不甲斐ない父親にイラついている娘のあかねは、半ばやけくそ気味に「今日、パーティをしましょう。誰でも来てください」と地図付きでツイートしてしまう。あっという間に拡散したこのツイートにより、数年前に恋人を作って家を出て行った元妻・昭子をはじめ、酔っ払いのOL、恋人を探しているイラン人、謎のホームレス老人などなど、さまざまな人びとが豪邸にやってくる。どんどん増え続ける珍客たちによって、豪邸はドンチャン騒ぎを超えた、狂喜乱舞の状態になっていく。
満足度
(3/5.0点満点)
鑑賞直後のtweet
映画「脳天パラダイス」
豪華キャストでやりたい放題!路線自体は大好きなんだけど。キメたんだから、徹底的な爽快感とか爆笑とかを求めてしまうんだけどなぁ。むしろ変な残尿感、なんだよなぁ。テンポが悪いのかなぁ。いとうせいこうと、柄本明が、実は似過ぎてる発見。シティボーイズ思い出す。 pic.twitter.com/gUqh6jEhMw— てっくぱぱ (@from_techpapa) December 10, 2020
感想(ネタバレあり)
ラリった時に見る夢って、こんな夢なのかなぁ、と思った。ま、ラリった事ないけれど。笑
トランスムービーだから、元々そういう狙いなんだろうな。とにかく豪華キャストで、パーティの設定を借りて、ハチャメチャやり放題。脳天がパラダイスになる、お花畑を楽しめばいい。私は、元々そういう話かな、と思って見に行っていたので良かったけれど。全く知らなくて、ハッピーな映画かな、なんて思って見に行った人は、ビックリするだろうなぁ、この展開。・・・そんな人がいるのかどうなのか分からないけれど。
面白かったシーンは。
結婚式を挙げに来たゲイのカップルが面白かったなぁ。あのドレス着ている男性、なんていう俳優さんだろう。
古田新太の役所が、あまりにも微妙過ぎて、逆にそれが面白い。「最初に言っとくけど、マズいよ」って最高。
南果歩と子供たちがお風呂に入るシーン。あれ、あの男の子どんな顔して入ったのかな、とか考えると可笑しくて仕方ない。
慰謝料を請求しに来た、台湾の元愛人のスピーチは、何だかほろっとしてしまった。みんなが聞いてないのに真面目に話す話、っていうの、シチュエーションの構図が面白いな、と思ったり。(親戚のオッサンのスピーチも同じ構造だよな。ただ、この女性の話はとても染み入るけれど)
ドトールのコーヒー豆の怪獣と、ピッチャーでコーヒー飲むのも面白い。インド映画風のダンスも好き。
で、見終わった後、もっと爽快感というか、脳内から邪気が抜けた感覚みたいなのを期待していたんだけれども、・・・意外とモヤモヤした感覚が残った。なんだろうなぁ。途中からテンポが悪いような気がしたんだけれど、それが原因かなぁ、と思ったりもした。太古の音色で、四つ打ちビートで、強制的に物語を展開していくとか、そういう乗せ方が欲しかったのかなぁ、と思った。
あと、柄本明と、いとうせいこう、って、すごく顔が似てるんだなぁ。近くで撮ったいとうせいこうの顔を見て、そんな事を思う。シティボーイズのコントの時もそうだったけれど、こういうナンセンスな作品が似合うな。
感想を書きながら調べていて、びっくり。好きな劇団、コンプソンズの金子鈴幸が脚本を担当していた。
過去の観劇
- 2024年10月18日【観劇メモ】コンプソンズ「ビッグ虚無」
- 2024年04月19日【観劇メモ】コンプソンズ 大宮企画「映画のパロディ」
- 2023年08月05日コンプソンズ「愛について語るときは静かにしてくれ」
- 2022年04月06日コンプソンズ「イン・ザ・ナイトプール」
- 2021年04月08日コンプソンズ「何を見ても何かを思い出すと思う」 ・・・つづき